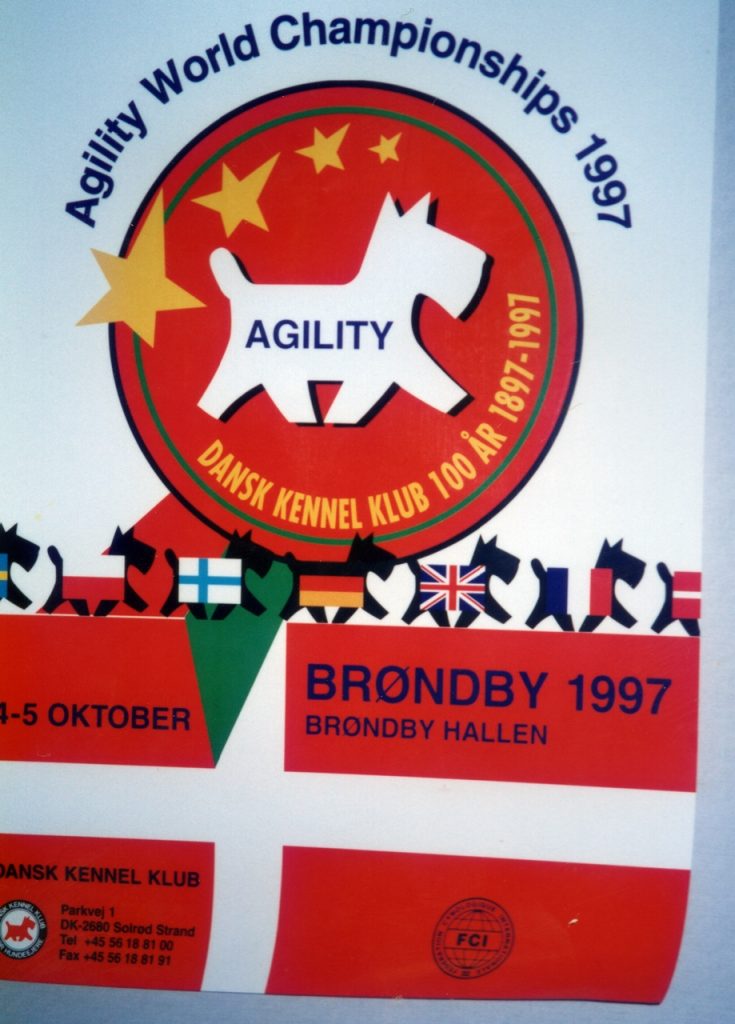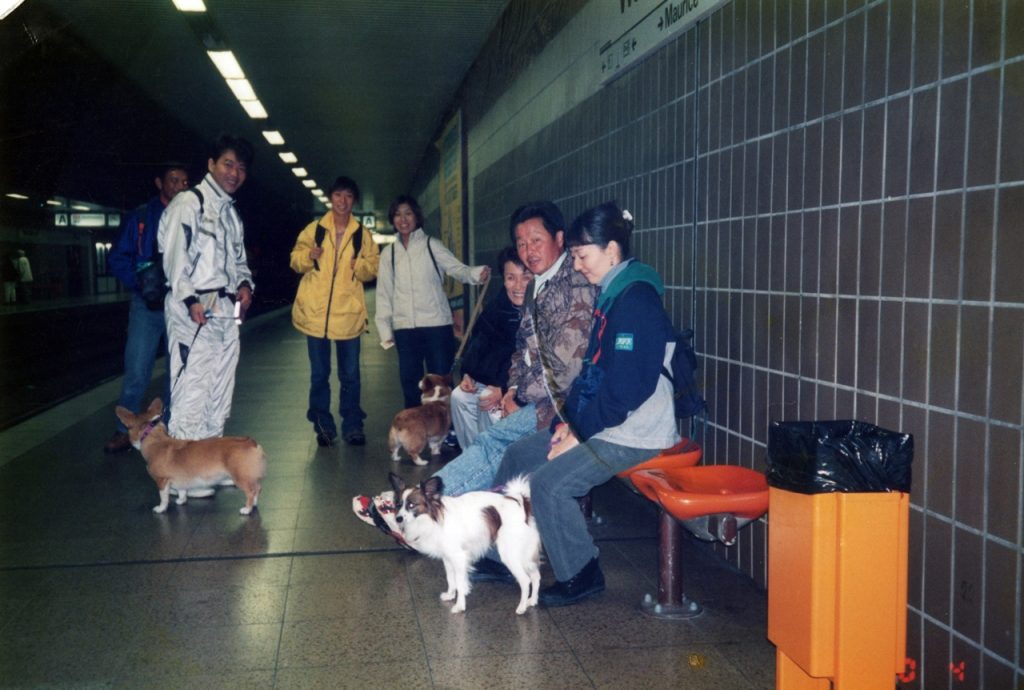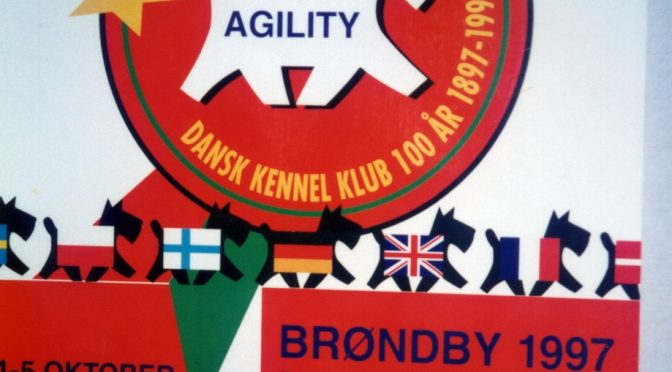2005年世界大会
日本快進撃
競技初日、個人戦;スモール:ノーミス、ノーミス、1ミス。ミディアム:ノーミス、ノーミス、ノーミス。ラージ:1ミス、ノーミス、ノーミス。標準タイムには少し引っかかったが、日本チームは失格0。サーキットペナルティーも二つだけだった。
二日目チーム戦決勝。ラージが5位。ミディアムが2位。スモールは11位。ミディアムの成績が光るが、ラージ、スモールも表彰台に肉薄している。ラージはミス3だったが、そのミスが一つでも少なかったら3位。スモールに至っては、失格がなければ優勝争いに加わっていた。失格は、PR間際の僅かなミスから生まれた微妙なものだった。
三日目個人戦決勝。スモール18位、32位、38位。ミディアム5位、8位、26位。ラージは残念ながら全犬失格。
全般、もちろん過去最高の成績。ラージの個人戦を除いては失格が圧倒的に少ない。惜しかったのは、三日目の個人ミディアムの内藤さん、普通の状態のステラで走らせてあげたかった。今回の日本チームは大変ムードが良かった。世界戦は、いかにリラックスして走れるかにかかっている。その環境を作り上げたチームが表彰台に残る。今年の日本チームはそれが出来ていた。テクニカル面にこだわらず、メンタル面に的を絞って取り組めたことは、今までの経験が生きたと言える。
表彰台
1996年、スイス大会に日本は本部競技会の成績の良かった4頭の犬を参加させた。当時、ヨーロッパ選手権として開催されていたアジリティーの大会は、この日本参加を機に世界大会と名称を変える。以来10年、日本のアジリティーは紆余曲折を経て、念願の表彰台に立った。先ずは、その日本チームの快挙に拍手を送りたい。
苦節10年、ようやくの表彰台だが、機が熟しての表彰台のような気がする。世界大会で問われるのは個人の技量ではない。その国のアジリティーである。代表選考のシステム,サポーターの協力、そして何よりそれらを支えるアジラーの層の厚さが必要である。
今回大会最後の日には、バレーでお馴染みの「日本チャチャチャ」の応援が会場中になりひびいた。他の国も自分の国の応援に[日本チャチャチャ]を使ったほどだ。地道なサポーターの努力の結果である。このようなサポートにはじまる、日本のアジリティーの環境が整って、得るべくして得た表彰台だと私は思う。同時に、それが整う前に、弾みで表彰台に立たなかったことが日本のアジリティーには幸運だったと私は思う。
概要
では、今年の世界大会の概要から。
フランスが消えた。かつて常勝、圧倒的な強さを見せたフランスが今年は表彰に近寄れなかった。フランスアジリティーの崩壊である。皮肉なことにその最大の元凶は、栄光の時代を築いたクリスチンのような気が私はする。公式トレーニング、フランスのトレーニングは雑で荒かった。タッチを踏めなかった。自らにチャンピオンをもたらしたコンタクトの走りぬけが、今年はチームに悲惨な結果をもたらした。最近のコースは、走りぬけるよりも確実に止めたほうが後の処理が有利になるように配慮されている場合が多い。
クリステレ(フランス)
二人のシルビア
そのフランスとは対照的に、高い完成度を見せたのがドイツのトレーニングである。群を抜いていた。そのドイツのハンドリングの背景にはシルビアの存在がある。
シルビア
彼女のハンドリングがドイツを変え、支えているような気がする。特別なハンドリングをするわけではない。一つ一つのシーケンスや局面に対して、理にかなった合理的なハンドリングを冷静に実行しているだけだ。アジリティーを知り抜いている。シルビアは、スロベニアのシルビアとともに、それぞれのカテゴリーを圧倒的な強さで制した。ドイツはラージ総合2位にも入り、ラップこそイギリスのグレッグにとられたが、難コースの個人ラージのAGのコースで2,3,5位に入っている。ドイツアジリティーの勝利だろう。
結果
個人戦 1位2位3位(4位)
スモール:ロシア、スイス、スイス(オランダ)
ミディアム:スロベニア、ベルギー、ベルギー、(スロベニア1.89)、日本2.78
ラージ:ドイツ、ドイツ、イギリス(オーストリア)
スモール、ロシアのアンジェリナ、ミディアム、スロベニアのシルビア、そしてラージ、ドイツのシルビアとジャンピングのトップがそのまま逃げ切って個人戦を制す。ミディアムは、洞口さんが5席、内藤さんが8席に入る。ミディアムは個人戦も完全に表彰台の圏内にいる。ラージは上記した通り。
チーム戦
スモール:スイス1ミス、ロシア、スペイン(フィンランド)
ミディアム:フィンランド3.66,日本5.82、スペイン8.36、ラトビア
ラージ:南アフリカ5、イタリア5.58、ロシア13.04(ノルウェー16.44)、日本17.05
スモールはマーチン、コルネリアのスイスの両名が個人戦での実力どおりの力を発揮して優勝。日本は、タイム減点は少しとられているものの失格以外はノーミス。優勝したスイスが1ミスだったことを考えると、ほぼ互角と言って良いだろう。ミディアムは、結果的にタイムの争いになった。チームミディアムの決勝ジャンピングのコースで失格したのは僅かに3頭。ジャンピングのコースは、イージーだった。それがこのような結果を生んだのだろう。ラージは南アが連勝した。上位3カ国は、昨年と同じ国である。
競技別の成績
では、例によって記録に現れないここの競技別の成績。
1チームAG、スモール:イタリアのアンドレア、ジャックラッセルテリアでトップ。2位はベルギーのパトリック(シェルティー)、3位はカナダのシーナ。4位はお馴染みスペインのアントニオさん、5位はフィンランドのウルフのコーギことスウェーデッシュバルフント。
ミディアム:チェコのラドバンがトップ。2位はイギリスのバーナデット禅(ZEN犬の名)。3位には内藤さんのステラが入っている。日本選手がはじめてベスト3に登場した。4はラトビアのシェルティー。5位はチェコのオルガ。
ラージ:トップはオーストリアの銀河、ハンドラーはミハエル・ブランドステッター。彼はチームの個人戦も制しているし、個人戦も総合で4位に入って来ている。今年の隠れトップ、注目すべきハンドラー。
ミハエル(オーストリー)
2位にはクロアチアのアレン(クロアチアシェパード)。3位もオーストリーのソーニャ。4位はドイツの刈上げの兄ちゃんフィリップ。5位は、アメリカのカウボーイことゲリー・ブラウン。
ゲリー・ブラウン、隣はマルコ(スイス)
2チームJP、スモール:ロシアの前チャンピオン、スベトラーナ・ツマノバ。これはハンドリングの勝利。2位はチェコのラドバン・リスカ、彼はスモールとミディアムをハンドリングしている。3位はイギリスのデービッド、ラージのデービットとは別人。4位スペイン。5位はチームAG3席のシーナ。
ミディアム:トップはフランスのピレネーシェパード。2位はベルギーのプードル。3位はチームAGで2位に入ったイギリスのシェルティー禅(ZEN)。4位はスウェーデンのプーミー。5位はチェコのシェルティー。
ラージ:1位は前記の通り。2位はイギリスのブルーマールのボーダー、ハンドラーはトニ(女性)。3位はクロアチアのアレン。アレンはAGも2位で、これが個人戦だったならチャンピオンだ。4位はご存知フィンランドのミコ。5位に健三さんが顔を出してくる。
アレンとサラ(クロアチア)
個人JP、スモール:トップは前記の通り、2位オランダのナターシャ。3位はドイツの
ジャックラッセル、ハンドラーはリンダーマン。4位5位は、スイスのマーチンとコルネリア。
ミディアム:トップは前記のシルビア。2位にチェコのラドバン。3位にスウェーデンのプーミー。4位、ベルギーのプードル。3位4位はチームのジャンピングでも上位に入っている。5位はラトビアのシェルティー(チームAG4位)。7位に内藤さんのステラが入っている。成績的には、これに注目が集まるだろうが、内藤さんはチームAG3位が光る。
ラージ:ドイツ勢が1位2位。3位にイギリスのデービット。これがそのまま個人戦の結果となる。4位はアメリカのリンダ。5位にスペインの若手の星ヨルディが来る。
個人AG、スモール:1位スイスのマーチン。2位ロシアのエレーナ。3位にチャンピオンになったアンジェリナ。4位シーナ。5位はスイスのアレクサンドラ(シェルティー)。
ミディアム:シルビアがトップ。彼女は完全優勝。2位にカナダのシェルティー、ニトロ。3位はアメリカのジーン(シェルティー)。4位ベルギーのプードル。5位オランダのシャロン(シェルティー)。6位に洞口さんが絡んでくる。
ラージ:グレッグがトップ。彼は最後の最後にようやく一矢報いることが出来た。それほどひどい走りだった。らしからぬミスが続出し、声をかけるのも気の毒なほどだった。公式トレーニングを見たとき、イギリスは彼を中心に回っているようだった。その彼が個人ラージのジャンピングでいきなりこけた。それが響いたのだろう。この最後の競技個人ラージ決勝の走りは、絶対確実という走りだった。にもかかわらず、ラップを取ったのだからたいしたものだ。2位にドイツのフィリップ。総合2位のドイツ人とは別人、刈上げのフィリップ。大喜びだった。
フィリップ(ドイツ)
3位にシルビア。4位にチェコのパワーあふれるマリノア。5位に総合2位に入ったドイツのフローリアンと続く。以下、総合3位のデービット(イギリス)。フランス、フレデリック。銀河のミハエラ。ニコラ・ギャレット(イギリス)とつづく。
コース傾向
| | PR | 失格 |
| スモール | チームAG | 73% | 17% |
| チームJP | 34% | 15% |
| 個人AG | 23% | 23% |
| 個人JP | 6% | 29% |
| | | |
| ミディアム | チームAG | 48% | 26% |
| チームJP | 48% | 5% |
| 個人AG | 12% | 24% |
| 個人JP | 10% | 23% |
| | | |
| ラージ | チームAG | 52% | 12% |
| チームJP | 37% | 18% |
| 個人AG | 32% | 42% |
| 個人JP | 31% | 15% |
個人ラージAGの失格の多さ、チームミディアムJPの失格の少なさが顕著。
PRはスモールとミディアムの個人JPが低い、これは標準タイムの設定によるもの。標準タイムは4.5m/sでセットされていた。ミディアムの個人AGもタイムに引っかかったのが多かった。アジリティーのコースで、4.6m/sで回っても標準タイムをクリア出来ないのだから無理なかろう。ジャッジはいずれもJOSEPさん。チーム戦は概してPRが高い。これはチーム戦を考慮したためだろうか。
ポルトガルのレスラーことドミンゴ、彼のボーダーはなかなか良い
停滞?
年々進化し続けてきた世界のアジリティーが、後退したような印象を受けたのは私だけだろうか。あるいは、日本のレベルが上がったのだろうか。世界大会のコースが、今年は簡単だった。レベル1かと思うようなシーケンスを含んでいるものまであった。競技であるから、それなりの難しさはあるだろうが、コースとしての面白みには欠けていた。何回もトライしたいと思うようなコースは少なかった。その中で最後の競技となった個人アジリティーのラージのコースは、ベルントさん会心の作だと私は感じた。日本へ帰ったら是非組み立ててトライしてみたい。
意欲に欠けて走らない犬が何頭かいた。これまでに無い事だ。運動能力に欠けるハンドラーも目立った。その人達が激戦を制して代表になったのなら拍手を送りたい。しかし、そのレベルの選手しか代表に出来なかったとしたら、レベルの低下である。スペインはヨーロッパにとってはやや外れている。そのせいだろうか。
課題
日本は、表彰台の常連になるだろう。それは間違いない。日本の、チーム戦に絞った選考システムは、世界大会にマッチしてきた。同時に成績不振の最大の課題に対して、ようやく回答を見つけた。しかし、課題は残った。今年のコースは、大会最後の個人ラージのコース以外は、これまでの世界大会の傾向から見てイージーだった。その唯一難しかったコースで日本は三つとも失格してしまった。これは課題だろう。そして、良い課題を得たと私は思う。今回の日本チームの成績は、その土台に日本の国内戦がある。チームとしてのまとまり、選考システムももちろん重要であるが、土台になっているのは国内戦である。その国内戦に向けて良い課題が出来たといえるだろう。スペインはとても美味しかった。成績も良く、行って良かった。来年はスイス、美しい国である。スイスは、もう少し時間に余裕を持って行ってみたい。
来年の世界大会ジャッジ キンドルさん